落款印(雅号印)とは、書道や画の作品が出来た際にする署名捺印のことです。
中国では唐代、日本では室町時代あたりから落款印が入れられるようになりました。
書道をしていると、落款印(雅号印)が必要になります。
はじめて落款印(雅号印)をオーダーし、印を作成してもらうとき、不安なことや疑問点がでてくると思います。
今回も書道ストーリーを通して、落款印(雅号印)を注文して手元に届くまでの流れをご紹介いたします。
書道短編小説 落款印篇
落款印(雅号印)の購入
「すみません、はじめて展覧会に自分の書道作品を出すので、作品に押す落款印をオーダーしたいんですが。」
店内で印泥を選んでいたお客様が、出荷作業をしていた私に話しかけてこられた。
その女性は、堺市内にお住いの片岡さんというお客様だ。
片岡さんは、定年退職をキッカケに、近所の書道教室に通うようになり、2年程書道に取り組んでおられる。
「書道作品の大きさは、もうお決まりですか?」
「漢字作品を半切サイズに書きます。作品の大きさによって、落款印の大きさは変えた方がいいんですか?」
「そうですね。漢字の半切サイズであれば、8分角くらいがよいですね。」
そう言って、篆刻印材の棚から青田青白章(青田石)の24mm角の印材を選んで、片岡さんに手渡した。
| 落款印の目安サイズ(mm) | ||
| 紙のサイズ | 漢字 | 仮名 |
| 全紙 | 21〜30 | 18〜24 |
| 半切(条幅) | 18〜24 | 15〜21 |
| 尺八 | 21〜30 | 15〜21 |
| 全懐紙 | 15〜21 | 9〜15 |
| 半紙・半懐紙 | 9〜15 | 9〜15 |
| ハガキ | 6〜12 | 6〜12 |
「印を押したときに、文字が白い印か赤い印どちらの種類がよいですか?
ちなみに白い方が白文、赤い方が朱文と言うんです。」
「赤い方がいいかな。朱文っていう方ですね。朱文か白文って好みで決めていいんですか?」
「最近は好みで選ばれる方が多いようですが、本来雅号印は朱文、名前は白文というルールがあります。
※雅号(本名以外につける風雅な名前のこと)
ルール以上に大切なのは落款印と作品のバランスです。
作品や紙の色に負けないようにするには白文、明るく重たくならないようにするには朱文の印がオススメです。
まあ、最初に買う落款印は、好みで選ばれてもよいかもしれませんね。」
それを聞いた片岡さんは少し考えて、今回は朱文にすることにしたようだ。
「落款印の書体は、篆書体が一般的ですが、今回の落款印は篆書体でいいですか?」
「篆書体以外も出来るんですか?」
一瞬困った顔になった片岡さんは、上目づかいで質問。
「出来ますよ。但し、篆書体で落款印をつくっておけば、作品内容を選びませんし、作品の格を下げませんから重宝すると思います。」
「じゃ、今回ははじめてですし、冒険せずに篆書体にしておこうかな。」
「落款印のお値段ってどのくらいするんですか?」
「当店では、印の大きさに関わらず、一文字税抜き3,000円と印材代です。」
今回の場合、巴林石に1文字ですので、4,180円(税込み)です。
※2020年1月5日現在の価格
「じゃあ、先にお支払いしておきます。」
そう言ってカバンから財布を出そうとする片岡さんに、
「お代は、落款印が出来上がってからで結構ですよ。」
落款印(雅号印)をつくるにあたって、どのくらいの金額が必要か分からず、かなり心配されていたようだ。金額を聞いた片岡さんは、「ホッ」と声が漏れそうなほど安心された表情を見せた。
書道作品に落款印(雅号印)は必要か?
一通り落款印作成にあたっての手続きが完了し、印泥選びを再開していた片岡さんが、
「ちょっと根本的なこと聞いていいですか?そもそも落款印って押さないといけないもんですか?」
確かに根本的ではあるけれど、とても重要なご質問だと思う。
「落款印は、自分の作品という証明として、落款や印を入れることになっています。
落款印自体が作品の一部と考えてもよいと思います。
絶対に落款印を入れなさいというルールはないですが、暗黙の了解といいますか、原則のようになっていますね。
白と黒で構成される書道作品にとって、朱色の落款印はとても重要な要素になると思うんです。
落款印を効果的に活用できれば、書道作品の格も上がりますよね。」
落款印(雅号印)のメンテナンス
2週間程で落款印が仕上がったので、片岡さんにお電話を入れると、その日のうちに取りに来られた。
出来た印をお見せすると、どうやら気に入っていただけたようだ。
とても嬉しそうにされていて、こちらも嬉しくなる。
「落款印のお手入れのご説明をしておきますね。
使われた後は、必ず印面に付いた印泥を紙や布で拭き取ってください。」
そう言って、片岡さんの前で印を拭いた。
「あと、あらかじめ毛の柔らかい歯ブラシをご用意いただいて、使用前にそのブラシで印面を軽くこすって、落としきれていなかった細かい印泥を掃除してください。
印泥が目づまりすると、線が潰れたり、不明瞭になったりします。
印泥が目づまりした落款印で押印すると、書道作品に大きな影響がありますからね。
つまった印泥がどうしてもとれない場合は、爪楊枝を使って、慎重に取り除いてください。
普段の落款印の保管は、印箱に入れたり石のキャップ(袴)がありますので、活用してください。」
「石である以上、誤って落としたりして、欠けてしまうこともあると思うのですが、そんな場合はどうしたらよいですか?」
「書道や篆刻などの世界では、印は古びた感じを好まれるので、印の完成前には撃辺といってわざと端を印刀で叩いて古風な味わいを演出します。
ですから、少々印が欠けても気にすることはないですが、見た目に明らかな損傷に見える場合は、残念ですがつくり直す必要があると思います。」
多くの場合、日常起こりうる衝撃には印箱や石印キャップで対応出来るが、落款印(雅号印)は硬い素材であるため、衝撃には強くないし、使い続けることで、少しずつ擦れるもの。
だからこそ、大切に使っていただきたい道具だ。
落款印/雅号印の作成承ります
https://www.osakakyouzai.com/products/list?category_id=258
書道ショートストーリー 第1回目 プロローグ
書道ショートストーリー 第2回目 羊毛の穂先短い書道筆
書道ショートストーリー 第3回目 おすすめの筆ペン
書道ショートストーリー 第4回目 淡墨の作り方
書道ショートストーリー 第5回目 落款印(雅号印)をオーダーする
書道ショートストーリー 第6回目 針切の臨書に適した小筆
書道ショートストーリー 第7回目 細光鋒の長い羊毛書道筆
書道ショートストーリー 第8回目 かな条幅の書道筆
書道ショートストーリー 第9回目 仮巻表装を依頼する
書道ショートストーリー 第10回目 額装された書道作品
書道ショートストーリー 第11回目 書道筆の洗い方
書道ショートストーリー 第12回目 半紙等の保存方法
書道ショートストーリー 第13回目 書道料紙を選ぶポイント
書道ショートストーリー 第14回目 色紙を書道用に使う
書道ショートストーリー 第15回目 竹筆の使い方 書道特殊筆
■■■■■■■■■■■■■■■■■
~書道ライフを快適・豊かに~
書道専門店 大阪教材社
FAX 072-277-6301
URL http://www.osakakyouzai.com/
E-mail moriki@osakakyouzai.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■
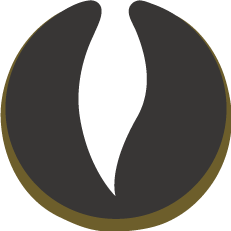


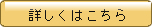

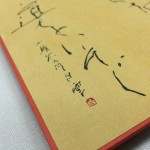



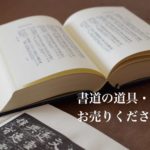




ピンバック: 仮巻表装を依頼する | 書道専門店 大阪教材社
ピンバック: 額装された書道作品 | 書道専門店 大阪教材社
ピンバック: 半紙などの保存方法 | 書道専門店 大阪教材社