書道専門店のエピソードストーリー第4回。
この回では、淡墨の作り方をご紹介します。
淡墨の読み方は、「たんぼく」です。
淡墨とは、墨を通常よりも薄めて使うことで、濃い色のときには分からなかった墨の青みや茶色みをいかした書道表現が可能な墨の使い方です。
それでは、淡墨に関する書道専門店でのお話しをご紹介いたします。
書道短編小説 淡墨の作り方篇
淡墨をはじめる

今日は、朝からパソコンに向かってホームページの更新を行っている。
最近は、スマホやタブレットでネット検索する方が増えているので、弊社のショッピングサイトもモバイル端末で閲覧しやすいように手直ししていたのだ。
この作業をはじめてから、どのくらいの時間が経ったのだろう。
1日の発送作業が終わった16時から始めたこのパソコン作業だったが、いつのまにか外は真っ暗になっている。
そろそろ閉店の準備をしようかと席を立ったとき、1人の女性が店に入ってこられた。
「いらっしゃいませ。」
私の声の先にいるのは、全身黒色の服を身につけた20代くらいのアート系の女性。
「こんばんは。」
彼女はそう言って少し頭を下げると、早々に墨コーナーに向かい、固形墨を選び始めた。
その女性は、熟考体制で墨とにらめっこしていたので、控えめにお声掛けしてみた。
「お伺いしますので、お声掛けくださいね。」
「あっ、ちょっといいですか。淡墨用の墨を探してるんですけど、ありますか?」
「淡墨用の墨はありますが、普通の墨を淡墨用に選んでいただいても大丈夫ですよ。」
固形の墨を手に取って、
「この墨の桐箱を開けると、説明書と一緒に濃墨から淡墨の墨色のサンプルが入っています。
それを参考にお好みの墨色を選んでください。」
私は墨が入っている桐箱を開け、中に入っている墨色サンプルの紙をお客さんに差し出した。
「墨によって微妙に色合いが違うでしょ?この墨色サンプルで比較していただいてもいいですし、墨色比較のファイルがありますので、これとあわせてご希望に近い墨色を選んでください。」
そう言って、かたわらに置いていた墨色のファイルを開いた状態でその女性に手渡した。
それまで表情なく墨を物色していた彼女の顔から少し笑顔が漏れて、
「これは比較しやすいですね。思っている墨色は、淡墨にしたときに青っぽくなる感じかな。」
そうつぶやくように、奈良の墨メーカー呉竹製の母情を指していた。
母情は、表面に榊莫山先生の揮毫が金色に施された丸い形状の墨。
淡墨で使うと、やや青みが強めで、柔らかみのある墨色だ。
「こんなこと聞いていいのか分からないんですが、淡墨ってどうやって作ったらいいんですか?」
少し申し訳なさそうにこちらを見ていたので、ちょっと笑ってしまった。
「もちろん聞いていただいて、大丈夫ですよ。」
そう言って、私は淡墨の作り方を説明しはじめた。
淡墨の作り方
はじめに墨を濃く磨っておくことがポイントです。
その濃く磨った墨に、少しずつ水で薄めて好みの墨色を見つけるんですよ。
逆にたくさんの水を使って墨を少しだけしか磨らないのは、淡墨としてよい墨色が得られませんので、気をつけてくださいね。
使用する水は、軟水がよいと思います。
日本は、水道水も軟水だからよいのですが、ミネラルウォーターがベターです。」
「そうなんですね。じゃ、私はこの墨で淡墨に挑戦してみます。」
「この墨ならキレイな墨色の淡墨になると思いますよ。」
淡墨を墨液でつくる
「今回は固形墨で淡墨をつくりますが、墨液でも出来るんですか?」
「出来ますよ。固形の墨でつくる方がよいですが、淡墨に適した墨液を使えば大丈夫です。例えばこの墨液なんか淡墨向きです。」
そう言って、同じ呉竹さんの古心という墨液を商品棚から取り出した。
「墨液と磨った墨を混ぜるなんてことも出来ますか?」
「膠系の墨液と磨った墨を混ぜることも出来ます。にじみ方が変わるので、是非試してみてください。
色味の違う墨を足すのも面白いです。」
墨以外の淡墨のポイント
「墨以外で注意するポイントありますか?」
「他の道具を使うポイントとしては、、、
使用する紙は、キレイなにじみが出る手漉きの画仙紙を使ってください。
中国の画仙紙や和画仙もありますから、少量購入していろいろな組み合わせを探すと、比較出来て楽しいです。
書くときは、筆に墨をたっぷりつけて、書いてくださいね。
墨液を含んだ筆の穂先を硯で切って、墨量調整しない方がよいです。
使う筆は、好みもあるでしょうが、穂先の密度の濃い純羊毛が合うと思います。
書いた後は、吸取紙で水気をとったり、ドライヤーで乾燥させたりしないことです。
墨の粒子をいかすためにも、自然乾燥がベストです。」
「ありがとうございます。実は卒業作品に淡墨の作品をつくるんです。」
「そうなんですか!それはご相談を受けたボクにとっても責任重大ですね。
もしよかったら作品発表の展示見に行ってもいいですか?」
「もちろんですよ!見に来ていただけるんですか?」
「絶対見に行きます!
日程が決まったら、お手数ですけど、教えていただけますか?」
そう言うと、私は自分のメールアドレスが印刷された名刺を手渡した。
会計を済ませた女性は、お釣りと一緒にその名刺を財布に入れて、丁寧に挨拶してくれた後、墨の入ったレジ袋を抱えて店を後にした。
後日、私のメールアドレス宛てに卒業作品の発表会の案内が届いた。
覚えていてくれたことが素直に嬉しい。
卒業作品の発表会には、初日にお邪魔することにした。
学生さんのイベントということで、大学の文化祭のようなにぎやかな雰囲気を想像していたけれど、視界に入るだけで20人程の人が静かに鑑賞していて、絵画作品や立体彫刻など様々な作品が展示されている。
残念ながら、私には美術に関しての観察眼を持ち合わせていないけれど、どの作品も力強く、気持ちが作品から溢れるような力作ばかり。
そんな作品群のかたわらに、お目当ての作品はあった。
F12サイズのパネルに、漢字1文字に「龍」と書かれたその淡墨作品は、まるで龍雲のように、画仙紙と壁の白を優雅に漂っていた。
書道ショートストーリー 第1回目 プロローグ
書道ショートストーリー 第2回目 羊毛の穂先短い書道筆
書道ショートストーリー 第3回目 おすすめの筆ペン
書道ショートストーリー 第4回目 淡墨の作り方
書道ショートストーリー 第5回目 落款印(雅号印)をオーダーする
書道ショートストーリー 第6回目 針切の臨書に適した小筆
書道ショートストーリー 第7回目 細光鋒の長い羊毛書道筆
書道ショートストーリー 第8回目 かな条幅の書道筆
書道ショートストーリー 第9回目 仮巻表装を依頼する
書道ショートストーリー 第10回目 額装された書道作品
書道ショートストーリー 第11回目 書道筆の洗い方
書道ショートストーリー 第12回目 半紙等の保存方法
書道ショートストーリー 第13回目 書道料紙を選ぶポイント
書道ショートストーリー 第14回目 色紙を書道用に使う
書道ショートストーリー 第15回目 竹筆の使い方 書道特殊筆
~書道ライフを快適・豊かに~
書道専門店 大阪教材社
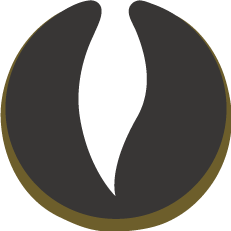



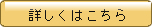

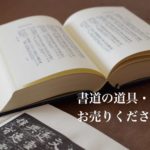








ピンバック: 墨の磨り方 | 書道専門店 大阪教材社
ピンバック: 一字書・少字数書とは? | 書道専門店 大阪教材社
ピンバック: 半紙などの保存方法 | 書道専門店 大阪教材社